参考文献&まとめ
まとめ 『廃市』 福永武彦著 日本文学全集17 河出書房新社
 『廃市』は十年前の記憶をたぐり寄せるように書かれた小説だ。大学生の僕が卒業論文を書くひと夏
『廃市』は十年前の記憶をたぐり寄せるように書かれた小説だ。大学生の僕が卒業論文を書くひと夏
のため、とある町の旧家にやってくる。快活な妹とはかなげな美貌の姉に出会う。
そこで姉夫婦と妹を挟む関係の末路に立ち会うこととなる。と書けば、おどろおどろしい想像をして
しまうが、流れる川のごとく、さらりとした読後感だ。
『廃市』は死都と呼んだ方がイメージが浮かびやすいかもしれない。
福永武彦がこの小説を書くにあったって、北原白秋の詩を添えた写真集、下記にある『水の構図』を
参考にしたことは有名だ。『廃市』の冒頭に「……さながら水に浮いた柩である」北原白秋『おもひ
で』とある。『廃市』という言葉も抒情小曲集『おもひで』に登場する。「私の郷里柳河は水郷であ
る。さうして静かな廃市の一つである」と。
風景描写が美しく、想像をかき立てるとの感想をほとんどのメンバーが持った。日本的な風景で、河が市内を流れている。そ
こそこ田舎であるとなれば、北原白秋の郷里でもある柳川が浮かんでくる。
福永武彦は一度も柳川を訪れたことがなく、日本ではないどこか架空の舞台を想定して書いたようだ。だが、白秋から多くの
着想を得ているので、読者としては、柳川を想像してしまうのは仕方がないことに思える。
今回は、福永武彦ファンであるエンゾさんに説明を頼んだ。福永武彦の生涯はトップページにある読書会の模様で、エンゾさ
んが概要を述べてくれている。
キリスト伝道師であった母と弟の死、友人の自死など、若くして多くの喪失を体験している。また、病弱であり、生涯を通じ
何かしらの病を患っていた。
福永武彦が愛読した北原白秋も、幼年期に世話をしてくれた乳母が自分が罹ったチフスに感染し亡くなる。親友の自死、大火
などによる家の没落、自身も病を患うことが多かったなど、共通点が数多く浮かび上がってくる。
北原白秋の『おもひで』に記された郷里柳河は、死のイメージを纏っている。亡なった乳母が幻のよう現れる詩、大道芸人に
売られた軽業の子どもを描くなど、美しさと共にもの悲しさが胸に染みてくるような詩が多い。
秋のたそがれを感じさせる。わたしはレイ・ブラッドベリの『10月はたそれがの国』を連想してしまった。
白秋が描いた『廃死』のイメージは少年の記憶であるのに対し、福永武彦は大学生の僕を選んだ。論文を書き終えれば大学を
卒業して社会に出て行くことが決まっている、未来ある青年だ。僕が体験するのは親しい人の喪失ではなく、男と女の不可解
な愛の末路だ。その前で、なぜか僕も愛に踏み出せず、時間の果てに置き去りにしてしまう。若いエネルギーを蓄えた僕です
ら『廃市』が持つ滅びの魔力に立ち向かうことができなかったのか。
滅びとは哀しい美しさがある。一歩引けば、触れてはならないほど完成された美とも思えてくる。だから読者は、こんな恋愛
の悲劇は成り立たないのではないかとの疑問も持ちながらも、先へと流されていく。残されるのは、淡い哀しみと緑深く、水
の流れる美しく寂しげな町の風景だけ。
『廃市』という小説は風景画に似ているとわたしは感じた。風景の中に人物が小さく配置されている。人もまた風景の一部な
のだ。思い描くのは西洋画だろう。白秋も影響を受けたローデンバックの『死都ブリュージュ』にある退廃とロマンチシズム
を、日本の風景で描きたかったのかもしれない。
廃市におけるイメージを写真や絵画を並べてみた。柳川の写真もいれているが、どれも同じイメージに見えてくる。
(廃市のイメージ.pdf へのリンク)←クリック
(編集・代表 椿野手毬)
参考文献 『水の構図』 田中善徳・北原白秋 (財)北原白秋生家保存会刊行
 (475x640).jpg)
写真家田中善徳と北原白秋により、水郷柳河の写真集。
白秋の故郷である水郷柳河。モノクロの写真風景に白秋の詩が添えられている。
初版は昭和18年。こちらは復刻版だ。当時は柳河で、近年柳川に改名された。
福永武彦はこの写真集『水の構図』を枕元に置くほど愛読していたらしく、そこから
『廃市』の着想を得たことは有名。
現在の柳川は整備され、風情ある川下りが有名の観光名所だが、川下りは昭和36年
からの創業となる。歴史は思ったよりも浅い。
現在の堀は生活用水路や交通網として使用され、暮らしの中に溶け込んでいた。
水環境のせいかチフスなどの伝染病も流行りやすく、火事もよく発生した。そのせいで
町は衰退に向かっていったようだ。
懐かしい日本の風景だが、モノクロのせいか華やかさはなく、哀愁を感じてしまうのは、
『廃市』を読んだせいかもしれない。
参考文献 『新潮日本文学アルバム・福永武彦』 新潮社
.jpg)
エンゾさんは母の影響で、福永武彦ファンになったという。小説は読んだが生い立ちまでは
知ることは少ない。
今回『廃市』を担当してもらうにあたって、人物像に迫る参考文献として、エンゾさん選ん
だのがこの本だ。
作家がどのような経緯を辿り、作品を書き進めていったのか、理解を深める入門書としては
最適である。
幼少期の写真など、本人の写真も多く、ファンにとって興味の尽きない内容となっている。
参考文献 『廃市』 大林宣彦監督 DVD ジェネオン・ユニバーサル・スタジオ
.jpg)
福永武彦を愛する大林宣彦監督が、私費を投じて撮影した映画。俳優やスタッフもボランテ
ィアで、興行収入を分配する方式で参加した。期間は2週間、不眠不休であったようだ。
福永武彦は生前、自身の作品が映像化されることを拒んでいた。彼の死後、夫人の許可を得
て撮影にこぎつけた。
初々しい小林聡美、陰のある美貌の根岸季依が出演。
1984年だから、20年以上前の作品だ。ちょうどこの辺り、若きわたし自身が訪れたことも
あり、うっそうとした柳が川面に映る風景に懐かしさを感じた。
『廃市』の雰囲気が素晴らしい。
柳川市民も協力を惜しまなかったが、当初『廃市』という題名に不満を唱えていたが、撮影
が終わる頃には映画を誇らしく思われたようだ
柳川でありながら、どこか見知らぬ幻想的な町に見え、風景の美しさが心に残る。
参考文献 『死都ブリュージュ』 ローデンバック著 岩波文庫

薄い文庫本だ。『死都ブリュージュ』という言葉のイメージに惹かれ、訪れた人も多いので
はないか。実はわたしもそうだ。
ローデンバックは永井荷風が愛した19世紀末び象徴詩人だ。
若い妻を失った詩人が、世をはかなんで、運河が張り巡らされたブリュージュを訪れる。
世捨て人として暮らし始めたが、亡き妻そっくりの女性を見かけ、破滅へと向かっていく。
挿絵も美しく、運河を取り囲む石の家々や教会が静まりかえり、死のイメージを醸し出す。
実際のブリュージュは大勢の観光客で賑わっている。ただ、夕暮れ時、観光名所からはずれ
た場所に迷い込むと人影が消えた。教会の鐘だけが響いてくる。物寂しい夕陽が石の町並み
を照らし,死都ブルージュに出会えたと思った。そんな空気を味わったことを思い出す。
白秋はもとより福永武彦も読んだろうと推測される。明治の文学少年たちに大きな影響を与
えたらしい? とはいえ、言葉の持つイメージは一人歩きするのだと実感する。
『死都ブルージュ』なんともロマンチックではないか。
参考文献『白秋望景』 川本三郎著 新書館
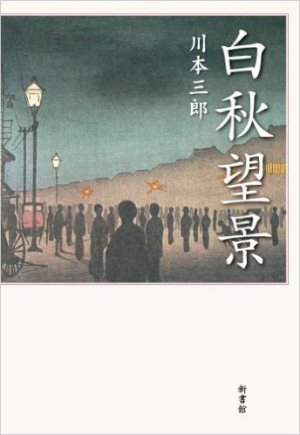
川本三郎による文学評伝。白秋の生涯が記され、白秋の遺した言葉、文学を読み解いていく。
裕福な造り酒屋に生まれたが、大火に遭い家は傾く。幼い頃チフスがにかかり、看病をして
くれた乳母が身代わりのように亡くなってしまう。
親友の自死など、相次ぐ悲劇ゆえ、郷里柳河は死と哀しみに彩られていた。
「わが生い立ち」で「水郷柳河は、さながら水に浮いた灰色の柩である」と書き記され「廃
市」のイメージが生まれた。
時代背景が「涙」を求めていたがゆえ、白秋のメランコリックな詩は共感を呼んだ。
読んでいくうち福永武彦も病弱で、白秋と共通点が多いことに気付かされる。
福永武彦が詩人白秋が紡ぎ出した『廃死』のイメージに共鳴するのは、当然の成り行きと思
われる。
『廃市』の参考文献として選んだが、興味の尽きない内容となっている。
たまたま柳川を訪れ、白秋記念館を訪問した直後なので、より身近なものになった。
伊藤整文学賞受賞。
参考文献 マチネ・ポエティク詩集 水声社
昭和28年、真善美社から750部発行された詩集の復刻版だ。
太平洋戦争最中、マチネ・ポエティク同人による同人誌で、当時の文壇からは認められなか
った。外国語を使うことさえ非国民とされた時代であった。
偶然、本屋で見つけ、迷った末に買い求めた。一期一会かもしれないとも感じた。
音韻定型詩、ほぼ14行で書かれている。
韻を踏みながら、古典的な言葉を多用する、ロマンティシズムを感じさせる詩が多い。
戦時下、文学の自由が失われてしまった環境で、詩を詩たらしめる形式に立ち戻る必要が
あったのかもしれない。
当時の閉鎖的な文学環境のなかで、自由を求め、定型詩の発表を試みた心意気を感じる。
福永武彦の詩は、廃市のイメージのごとく流麗さが際立っているように思えた。
最初の妻となる原條あき子の存在も興味深い。